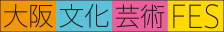-
ぴあ演芸館ウミガメ寄席 「春野恵子・神田松之丞 二人会」
-
-

-
春野恵子 神田松之丞 二人会 ~ぴあ演芸館ウミガメ寄席~ なぜ「ウミガメ」なのでしょう。オープニングでのお二方のトークでその謎はすぐに解けました。「日本には落語家が800人いますが講談師は80人。少ないでしょう」と松之丞さん。落語ブームといわれる昨今、同じ日本の伝統芸能なのに、講談、浪曲は認知度が低く、講談師、浪曲師は希少で「絶滅危惧職」(ぜつめつきぐしょく)といわれるそうです。いわば、絶滅危惧種のウミガメ=講談、浪曲を守ろう!と立ち上がったお二人というわけです。会場のロビーに絶滅危惧種の動物写真が展示してあるのも一興です。「浪曲、講談を聴くのが初めてという方は?」という松之丞さんの問いかけに客席から多くの手が挙がります。春野さん、松之丞さんは大げさにのけぞり「これは大変。面白くなかったら2度と来てもらえませんからね。しっかりやらなきゃ」と気合いのポーズ。お二人が講談師、浪曲師を志したきっかけや、裏話なども披露されました。
-

-
上演はまず「チケットが最も取れない」が枕詞の人気講談師、神田松之丞さんが登壇。大きな拍手と「待ってました!」の声が掛かりました。まくらで「講談が幕末から明治にかけて盛んでしたが大正時代にはもう時代遅れ」と言われたことや、「早口でまくし立てるしゃべり方なので、何を言ってるかわからない」と言われるという自虐ネタで観客を笑わせた後は、「源平盛衰記 扇の的」を披露。那須与一が船の帆先の扇の的を見事に射るというおなじみの話ですが、松之丞さんの釈台(しゃくだい)と呼ばれる小さな机を張り扇(はりおうぎ)で叩きながらのリズミカルで豪快な語りにググッと引き込まれます。静かな語りと会場全体に響き渡るような凛とした声、独特の抑揚で観客が前のめりになっていくのがわかります。クライマックスでは与一が扇の要を狙い、放った矢の行方が「どうなるどうなる~」と、何度も観客を焦らして笑いを誘います。まさに「空間を支配する講談師」の本領発揮といったところです。
次はゲストの落語家、桂春蝶さんが登壇。実父である二代目桂春蝶を継いで落語家になった春蝶さんは「だいたい三代目で店はつぶれるんですよ」などとまくらで笑わせ、子供のころに聴いて育った小噺や、扇子でかんざし、キセルなど小道具を表現するコツなども披露。落語の演目は、若旦那と芸妓・小糸の悲恋、上方落語の名作といわれる「たちぎれ」(立ち切れ線香)。春蝶さんの流れるような美しい語りと絶妙なオチに会場からは「ほーっ」とため息がもれていました。
-

-
中入り後は浪曲師の春野恵子さんが登場。某バラエティー番組での家庭教師・ケイコ先生として記憶されている方も多いのではないでしょうか。現在は古典浪曲と同時に、新ジャンル「ロック浪曲」「英語浪曲」などで、外国人や若者にも浪曲を広める取り組みを行い、ニューヨークなど海外8か国で公演。国内でも年間200回ほどの公演を行うなど日本を代表する浪曲師です。まず、浪曲は物語を節(ふし)と啖呵(たんか)で演じる浪曲師=春野さん、伴奏となる三味線の弾き手、曲師(きょくし)=一風亭初月さんで物語を演じました。浪曲はなじみが薄いかもしれませんが、シブガキ隊の「寿司食いねぇ」は元はといえば浪曲。広沢虎造の口上が元で~というような話がありました。また、浪曲の聴き方・拍手掛け声講座(?)も。浪曲師が入って来たら拍手と「待ってました!」とひと声。さらに、前口上(浪曲師の挨拶)のあとに「たっぷり!」ともうひと声。最後は「日本一!」「大統領!」で締めくくってねと指南。「では、私が入って来るところから~」と学習通りに始まったこの日の演目は、井原西鶴「好色五大女 樽屋おせん」。樽屋主人、女房おせん、麹屋長左衛門、嫉妬深いお内儀など声音をくるくると変える見事な啖呵、朗々とした節も声量があり聴きごたえ十分。曲師との呼吸もぴったりで、まるでジャズのセッションを聴いているかのような熱演で会場を沸かせました。
売れっ子講談師の松之丞さんは公演後すぐに次の会場に出発したため、春野さんがお客の見送りをしていました。会場には九州から駆けつけたという方や、ケイコ先生の頃から春野さんのファンという方も。直接感想を伝える方もいらっしゃいました。 至高の話芸を堪能して、改めて古典芸能の魅力が感じられる公演でした。
-